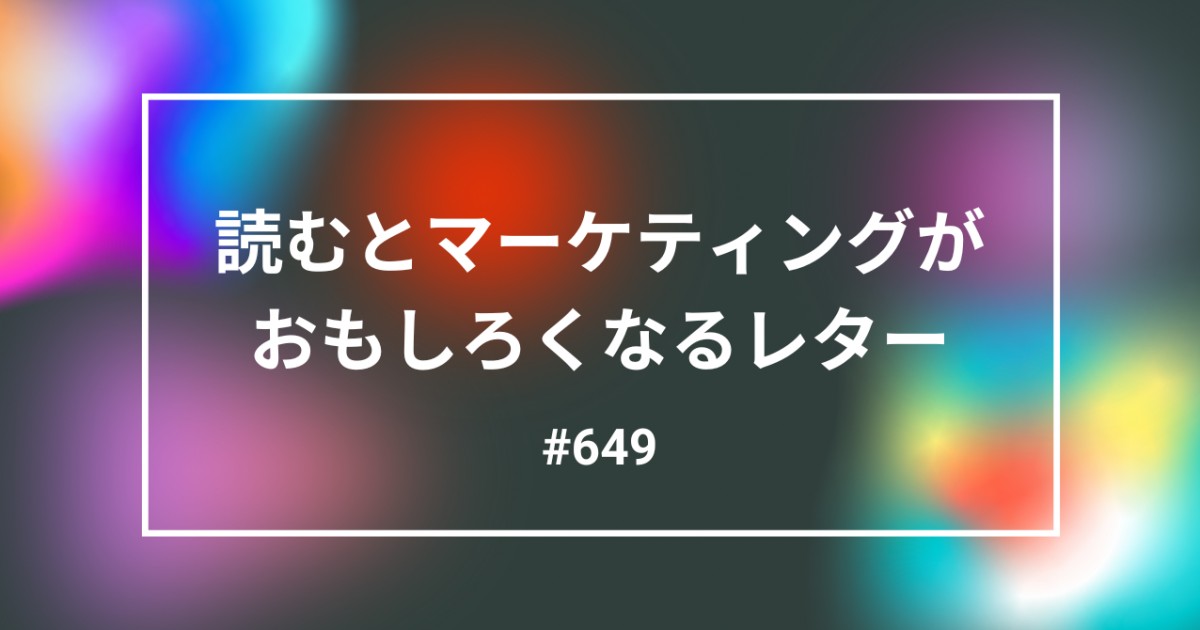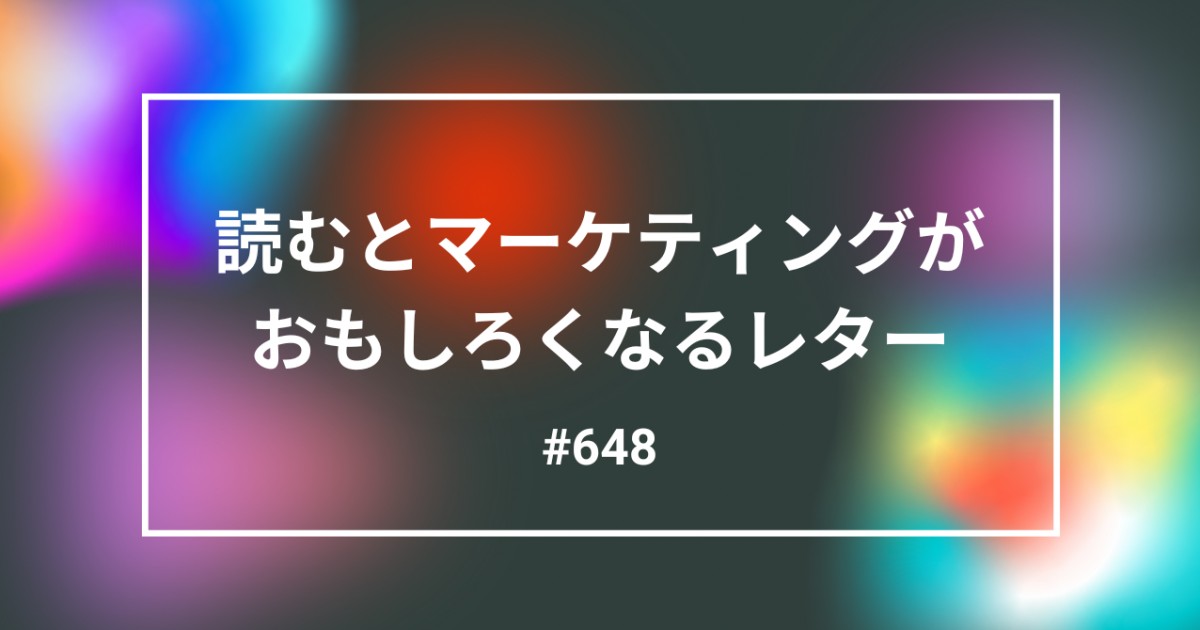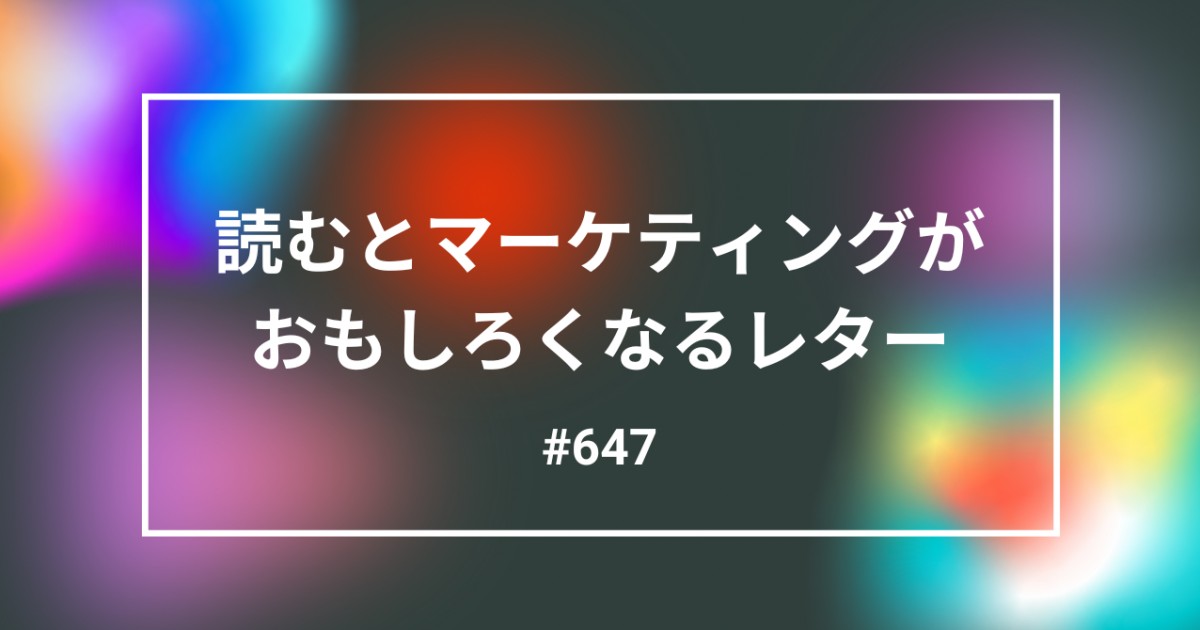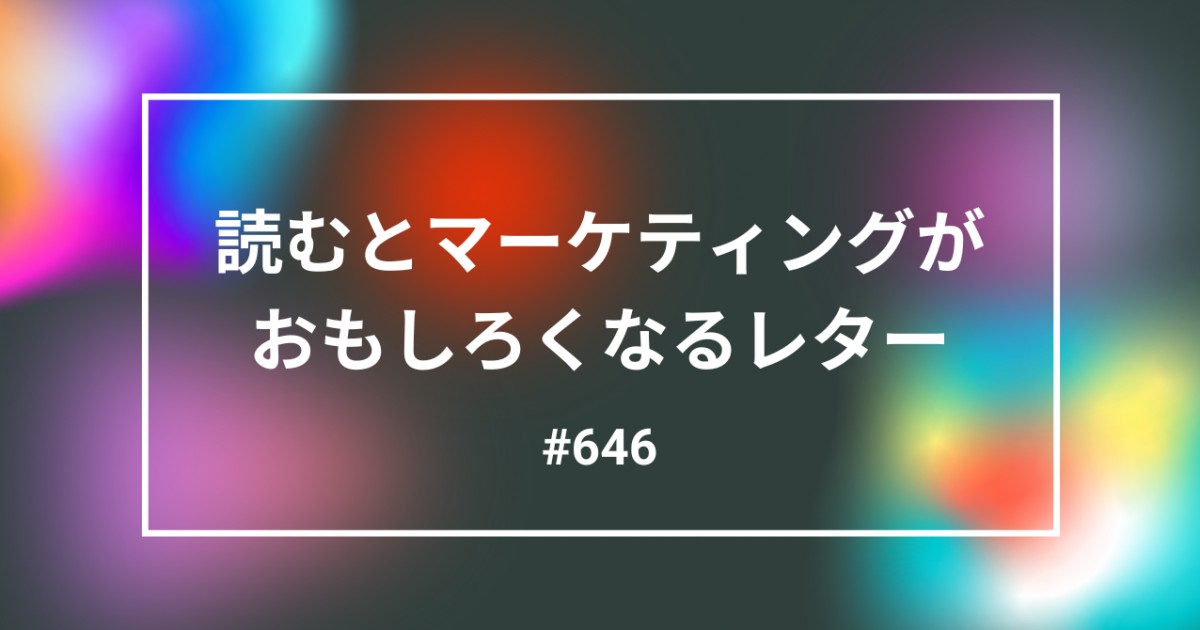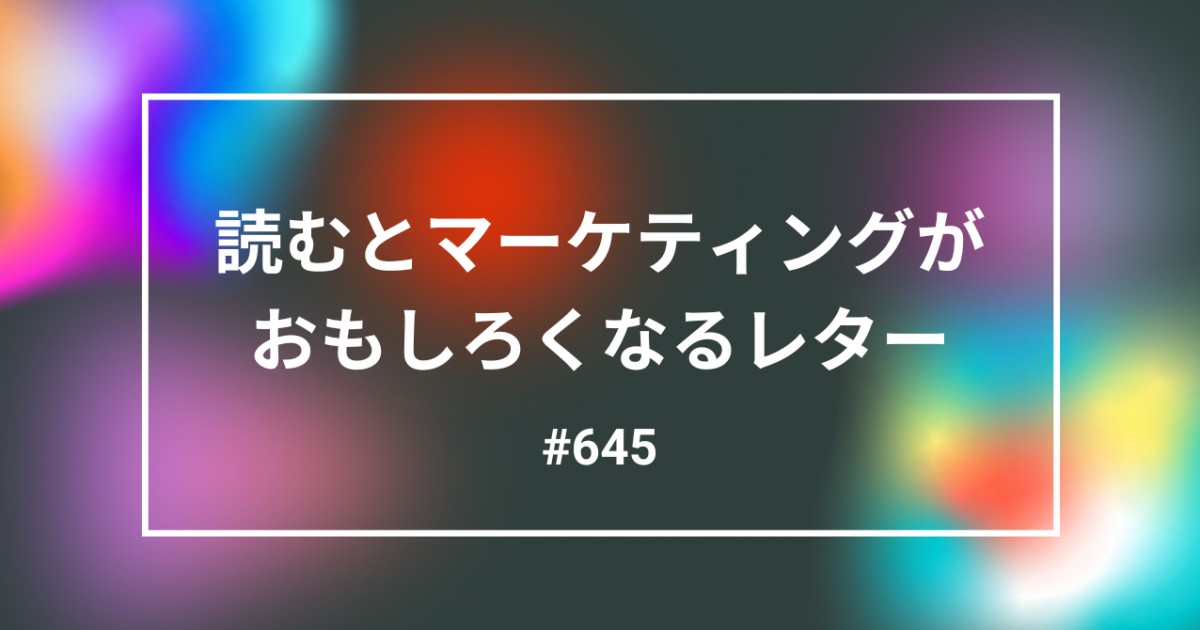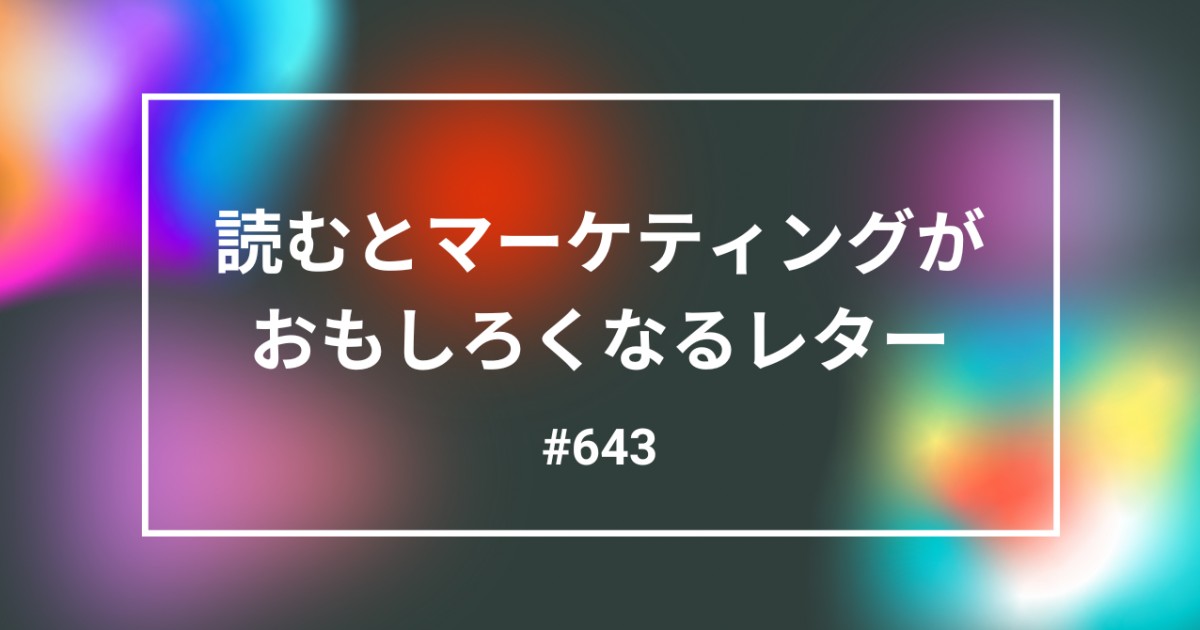#16 Google や Twitter の開発手法 「リーンスタートアップ」 で、あなたも一歩を踏み出そう
こんにちは。メールを開いていただきありがとうございます。
今回のテーマは商品やサービス開発です。
書いている内容は、
-
開発を小さく始める 「リーンスタートアップ」 をご紹介
-
[事例 1] Facebook, Twitter はサービス開始初期はこんな感じでした
-
[事例 2] Google にいた時の調査手法開発のエピソード
-
MVP 思考で小さく始めてみよう
このレターが、何かを新しく始める、挑戦する時のヒントや応援になればと思い書きました。
ぜひ最後まで楽しみながら読んでみてください!
プロダクト開発と仮説

商品・サービス開発のことを、これ以降は 「プロダクト開発」 と呼んでいきますね。
プロダクト開発の特に初期段階では、プロダクトアイデアはあくまで仮説です。仮説は検証をして初めて正しいかが分かります。裏を返せば仮説の時点では仮の答えにすぎません。
プロダクト開発では、アイデアという仮説の検証は、想定するターゲットユーザーに実際に見せたり使ってもらいます。
では実際のサービスで具体例を見ていきましょう。Facebook と Twitter です。
初期の Facebook
Facebook の初期のログイン画面は、次のようなものでした。

引用: Clearcode
初期の名前は 「Thefacebook」 です。
当初はハーバード大学の学生向けでした。創業者のマーク・ザッカーバーグがハーバード大の学生の時に生まれたサービスです。
この時点で今と変わらない仕組みがあるのが興味深いです。具体的には、
-
メールアドレスでログインする
-
大学の知り合いが探せる (Search for people at your school)
-
友人の友人とつながる (Look up your friends' friend)
Twitter のプロトタイプ
ではもう1つの初期プロトタイプの事例を、Twitter から見てみましょう。

引用: Clearcode
Twitter は初期の名称表記は 「Twttr」 でした (母音 (Twitter 内の i, e) がないですね) 。
おもしろいのは初期の時点で、すでに今の Twitter とサービス機能の原型があることです。
-
フィード機能の実装 (知り合いの 「今 ◯◯ をしている」 の投稿)
-
自分が今やっていることが投稿できる
機能はシンプルです。
色などの見た目は今の Twitter とは違いますが、Twitter のコアアイデア (フォロワーのつぶやきがフィード画面に流れる, 自分のツイート投稿が簡単にできる) が実装されています。
ここまで Facebook と Twitter がサービス開始初期にどのようなものだったかをご紹介しました。
ここからは、話を一般化して解説していきます。プロトタイプという未完成の試作品からサービス開発をつくっていくアプローチを解説します。「リーンスタートアップ」 という方法です。
リーンスタートアップ

プロダクト開発のアプローチに 「リーンスタートアップ」 があります。
リーンスタートアップは Facebook や Twitter 、他にも Google などで取り入れられている開発手法です。リーンスタートアップの Lean は、「俊敏な」 や 「無駄のない」 という意味です。
リーンスタートアップでは仮説立案と検証のサイクルを小さく早く回します。プロトタイプを作りテストし、このサイクルを何度もまわしてビジネスアイデアをブラッシュアップしていきます。
細かく刻むように進むので、もしアプローチが間違っていてもすぐに戻れます。大きな手戻りがなく、無駄が発生しません。
リーンスタートアップのサイクル
リーンスタートアップの特徴は、次のような6ステップのサイクルを回します。

引用: KBP Media
リーンスタートアップのサイクル
-
Idea (アイデアを得る)
-
Build (つくってみる)
-
Product (プロダクトになる)
-
Measure (テストをして測定する)
-
Data (データを得る)
-
Learn (学ぶ)
アイデアや仮説が生まれたら、まずはプロトタイプで良いので実装してプロダクトにします。
プロダクトをテストしデータを得ます。データとは例えばプロダクトテスト対象者からのフィードバックです。フィードバックから学び、アイデアや仮説に反映します。
以上を1つのサイクルにして繰り返していく手法がリーンスタートアップです。
ポイントはアイデアを得たらプロダクトという形にし、素早く試すことです。
机上の議論ばかりではなく、まずは手を動かしプロダクトというアイデアの具現化をします。やってみて初めてわかることがあり、そこから学びを得るのです。
リーンスタートアップのことは、リーン・スタートアップ - ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす という本に詳しく書かれています。もしよかったらぜひ読んでみてください。
まずは MVP をつくる

リーンスタートアップのアプローチで鍵を握るのが MVP です。
MVP は Minimum Viable Product の略です。Minimum は 「最小限の」 、Viable は 「実行できる」 です。MVP は日本語では 「実用最小限の製品」 と訳されます。ただ、実務の場ではこの表現は使われたことは私の経験では一度もなく、そのまま MVP と呼びます。
プロダクト開発の初期段階では原始的なプロトタイプとして MVP をつくります。ミニマムという単語が入っているように、MVP は開発には極力リソースをかけずに本当にテストしたい機能やデザインに絞った初期プロトタイプです。
想定する顧客に MVP を使ってもらい、仮説検証を進めます。検証したい論点と仮説を明確にし、仮説検証のための手段として MVP をつくるわけです。
MVP は仮説検証の手段
開発初期の段階では、プロダクトアイデアはあくまで仮説です。仮説が正しいのかを検証するために MVP があります。MVP は仮説ありきです。
大事なのは目指すつくりたいプロダクトがあり、最終ゴールから逆算して何の仮説を検証したいかが明確になっていることです。
例えば開発したいプロダクトが自動車だとします。この場合に NG な MVP と、良い MVP からの開発のイメージは次の絵のようなプロセスです (NG は上段、良いのは下段) 。
絵の補足をすると、プロダクトアイデアのコアになる仮説は 「人や物を運べるニーズが想定顧客にあるだろう」 です。ここから MVP としてスケボーを作ってみて、仮説を検証するわけです (上の画像の一番左) 。
ありがちなのは目指す作りたい自動車に対して、MVP はタイヤだけを作り込んでしまうことです (画像上段の右) 。いかにタイヤが素晴らしくても、これだけでは 「人や物を運べるニーズが想定顧客にあるだろう」 という仮説は検証できないですよね。
MVP は仮説があってこそで、仮説検証の手段です。
MVP のポイント
MVP のイメージで、わかりやすい絵をもう1つご紹介しますね。
MVP は 「Minimum + Viable」 の両方を満たす必要があるという絵です。

引用: Hacker Noon
この絵で最終的に作りたいプロダクトは、大勢の人を運ぶ船です (絵の右側の Maximum) 。ここから逆算をすると、MVP は人間が1人乗れるボートになります (絵の中央) 。ネズミが乗るようなボートではないのです (絵の左) 。
以上から MVP つくるポイントは3つです。
MVP のポイント
-
目指す最終形のプロダクトイメージからの逆算
-
今の開発ステージで優先的に検証すべき仮説の明確化
-
仮説が検証できる最小限の機能の実装
では、MVP をつくって開発を進めていくリーンスタートアップの事例で、私が Google にいた時のエピソードがあるのでご紹介させてください。
Google での調査手法開発の話

私が Google で働いていた時のサービス開発の話です。
当時はなかった、ある調査手法の開発エピソードです。まずは背景から共有しますね。
Google にいた時は私はマーケティング部門に所属していました。ポジションはマーケティングリサーチ マネージャーです。
当時取り組んでいたテーマの1つが、検索広告のブランディング効果の可視化でした。
広告のブランディング効果とは、広告を見て商品・サービスを知ったり、興味を持つ、買いたいと思うような態度変容や行動変容です。
検索をしたユーザーに検索広告が表示され、仮にその場で検索広告がクリックされなくても、商品・サービスを新たに知ったり、いいなと思ってもらえれば検索広告にブランディング効果があるわけです。
まずは小さく始めることから
しかし、検索広告にブランディング効果があるかを調査手法が、そもそも確立していませんでした。ないなら自分でつくってみようと思ったのが、開発の一歩目でした。
背景と問題意識、解決するためのコンセプト案をまとめ、調査手法イメージをスライドにまとめました。
ここでのポイントは 「小さく始める」 です。そもそもの問題意識やコンセプトアイデアの筋が良いかをスライドを使って検証しました (ペーパープロトタイプでの仮説検証) 。
次に 「ありもの」 で調査を再現

スライドでのアイデア仮説の検証からニーズはありそうで、「これはいけそうだ」 という実感を得ました。
次にやったことは、すでにある調査ツールを使って検索広告調査を再現しました。既存ツールとは Google が提供していた Google Surveys というセルフアンケート調査です。
テストをなるべく実際の検索広告調査として再現するために、社内の営業メンバーを巻き込み協力してくれる広告主を探しました。
賛同してくれる広告主が見つかり、実際の商品から検索広告を作り調査案件を再現しました。企画、設計、調査、分析、レポートと1人で全部をやった経験も、後から役に立ちました。
広告主からも好評価
テスト調査結果は広告主に報告をしました。
これまでに誰もやったことがない調査でしたが、結果だけではなく開発した新しい手法も興味を持ってくれました。広告主からは 「この方法があれば、こんな活用方法もできるのでは」 とフィードバックをもらえたことも貴重でした。
1つ目の開発ステップでスライドからのコンセプト検証をした時以上に手応えを得られました。
ただしこのやり方は既存の調査ツールを使った方法で、いわばパッチワーク的なアプローチでした。調査としては十分に機能するものの、手作業での対応があり案件が増えた時に受けきれないと思いました。仕組み化と案件量産体制への課題感です。
調査会社との共同開発へ

そこで仕組みとしてさらに発展させるために、調査会社に声をかけて共同開発をすることにしました。
これまでの開発経緯、調査手法、テスト結果を共有をして、賛同してもらえました。
検索広告のブランディング効果を可視化する調査メニューを作り、調査会社の有償サービス化が実現しました。開発の過程で、テストに協力してくれる広告主を新たに募り、複数社での共同調査が実現しました。
それぞれの広告主には趣旨を説明し、使わせてもらった商品・サービスの検索広告からの結果を本当の調査案件のように報告をしました。調査手法とブランディング効果の結果を評価いただき、ブランディング広告を可視化する調査メニューが正式に始動しました。
では以上の調査手法開発をまとめますね。
やったことを振り返ると、ホップ・ステップ・ジャンプの三段階でした。
調査手法の開発プロセス (3つのステップ)
-
問題意識やコンセプトアイデアをスライドにまとめ (最初の MVP) 、ヒアリングからアイデア検証
-
既存調査ツールで検索広告のブランディング効果測定調査を再現 (2つ目の MVP) 。広告主から好評価とフィードバックを得た
-
調査会社と共同開発。複数社の広告主と調査を実施。ブランディング広告を可視化する調査メニューが有償サービス化した
なお、この調査手法を使った結果は Google のオウンドメディアである Think with Google で発表をしました。
よければこちらもぜひ読んでみてください。
MVP 思考

プロダクト開発で MVP を使うやり方は、一般化すれば汎用的にビジネスで広く当てはまります。
何か仮説を検証する時に考えると良いのは、どうすれば検証できるか、最小限のリソースと手間で検証するにはどうすればいいかです。
この時に MVP を使って仮説検証をする方法が活かせます。「これの MVP とは何か」 を問いかけてみるのです。これが MVP 思考です。
小さく始めてみよう
MVP 思考とは、「小さく始めよう」 です。
いきなり大股の一歩を大きく踏み出すのではなく、半歩でもいいので小さく進みます。小さく刻むように進めば、もしその方向が間違っていたとしてもすぐに戻れます。ビジネスの文脈に話を戻せば仮説を作り直せます。
しかしもし大きく出てしまうとリソースを多く使ってしまっていて、また、その分だけ戻るのに時間がかかります。
よかったらぜひ何かを始める時には、MVP 思考から小さく始めてみませんか?
今日のアクション
そろそろ今回のレターも終わりです。ここまで読んでいただきありがとうございます。
このレターの毎回に共通するコンセプトは 「Question Insights Action」 です。意味は、問いかけに対して示唆を得て (Insights) 、半歩でもいいので行動につなげてみませんか (Action) 、というものです。
今回のレターでの問いかけは、「あなたにとっての MVP (実用最小限の製品) は何ですか?」 です。
ここで言う MVP とは、目指すことから逆算した最初の一歩目のことです。ただし、あまり難しく、堅苦しく考えなくてもいいと思うんです。
一歩目は間違ってもいいし、大事なのはまずはやってみることです。やってみて違うと思えば引き返し、別の一歩を踏み出していけばいいんです。MVP の M はミニマムで、もしかしたらあなたの一歩はまわりの人には気づかれないくらい最小限かもしれません。
でも何より大切なのは、自分が歩みをスタートさせたことなんです。ぜひ半歩でもいいので小さく始めてみませんか?
質問・リクエストを募集しています
もしご質問やリクエストがありましたら、こちらの匿名の質問箱にぜひコメントください!
-
疑問に思ったこと
-
訊いてみたいこと
-
自分なりの理解や解釈
-
レターへのリクエスト
いただいたご質問やリクエストはレターでも取り上げられればと思っています。
ぜひ質問・リクエストを教えてください!
レター作成者
多田 翼
Aqxis 合同会社 代表 (会社概要はこちら)
経歴
Google でシニアマーケティングリサーチマネージャーを経て独立。Aqxis 合同会社を設立し代表に就任。Google 以前はインテージにてマーケティングリサーチ業務に従事。
京都大学大学院 工学研究科 修了。
主な事業
マーケティング, マーケティングリサーチ, 事業戦略などのコンサルティング事業
※ お問い合わせは会社 HP からご連絡ください
・マーケティングのことが学べる
・人気商品のヒット理由がわかる
・仕事でマーケティングや商品アイデアのヒントになる
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績