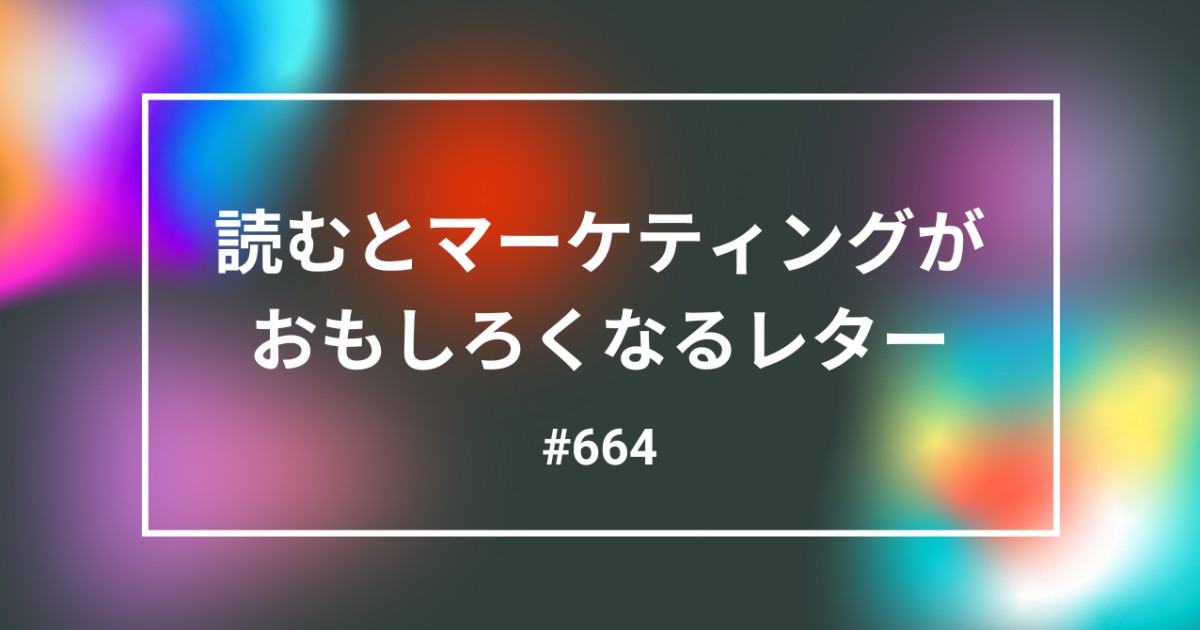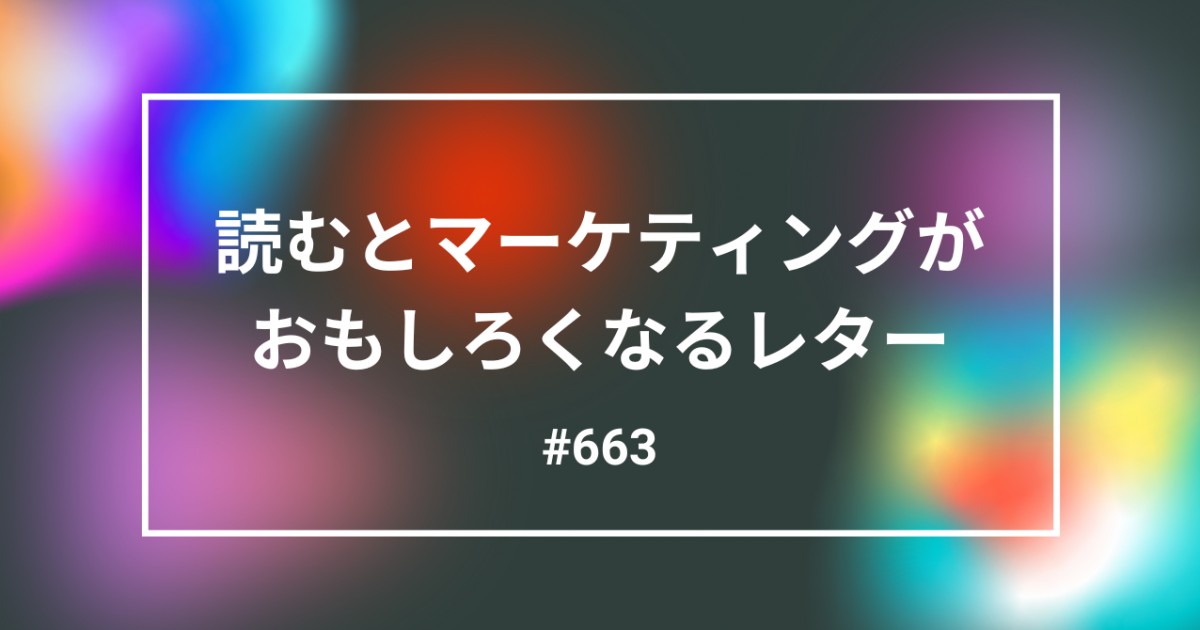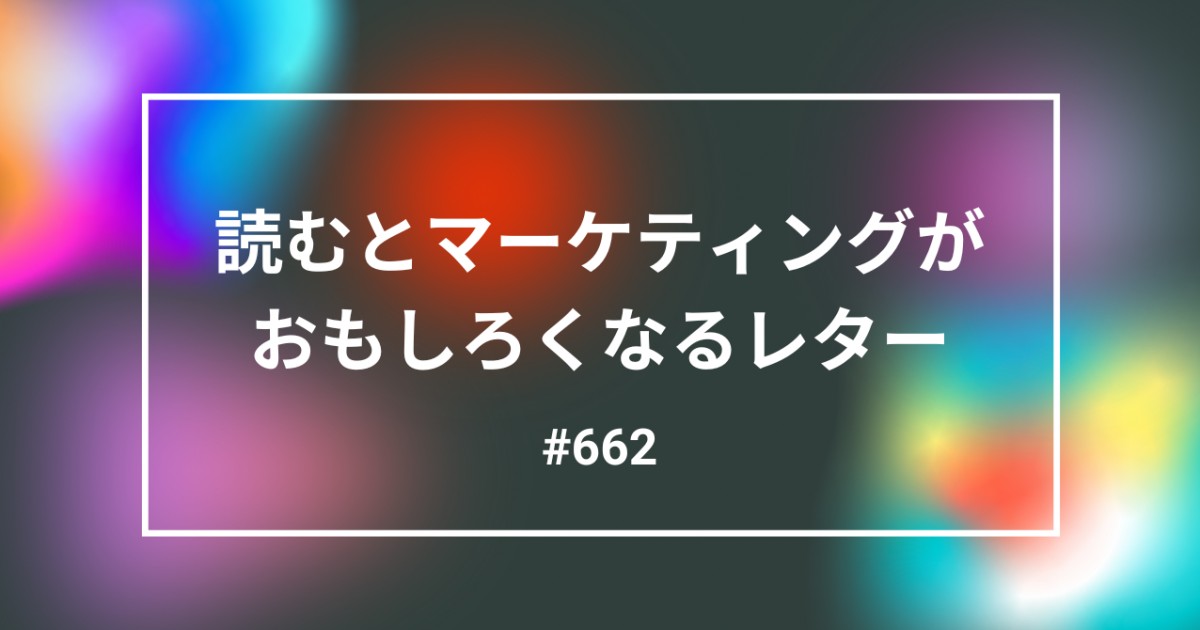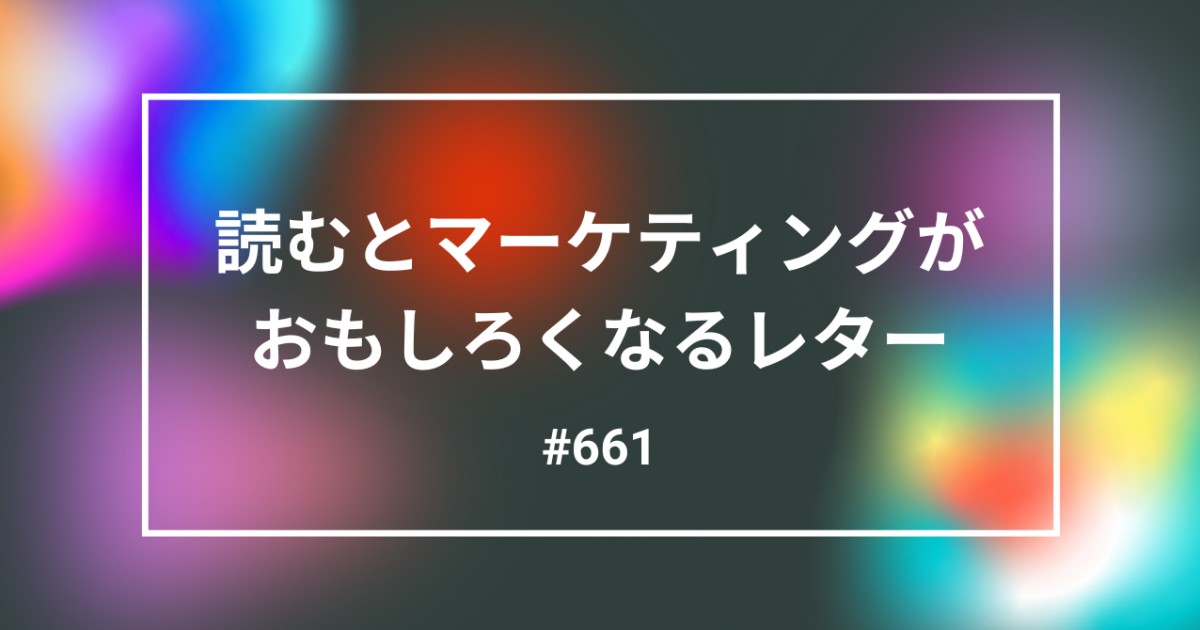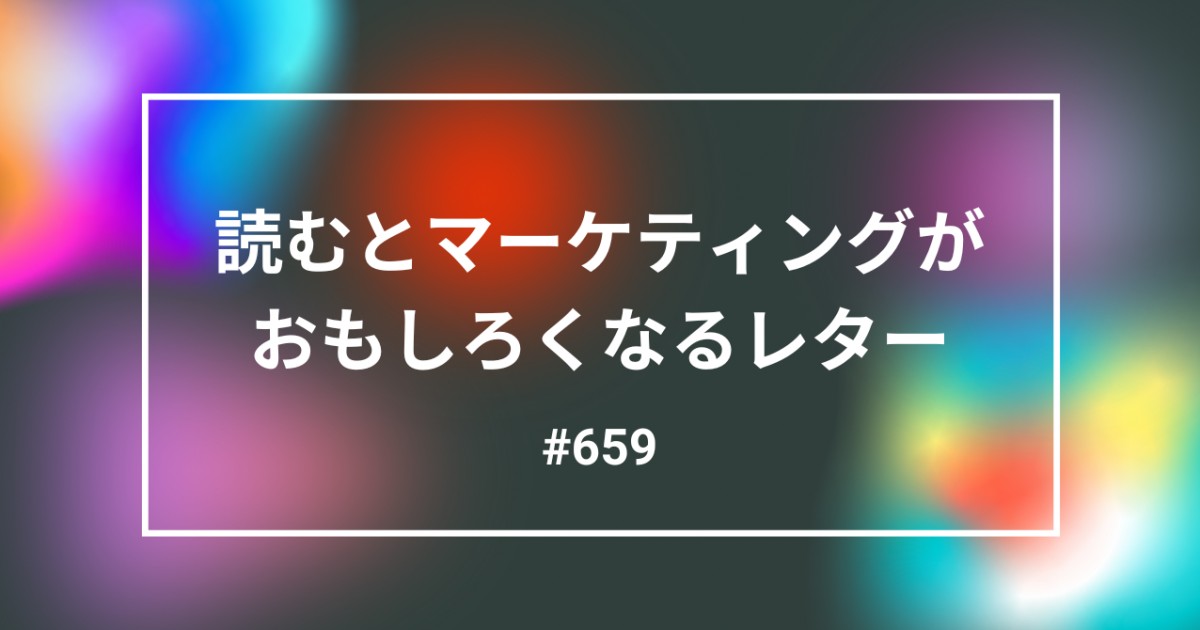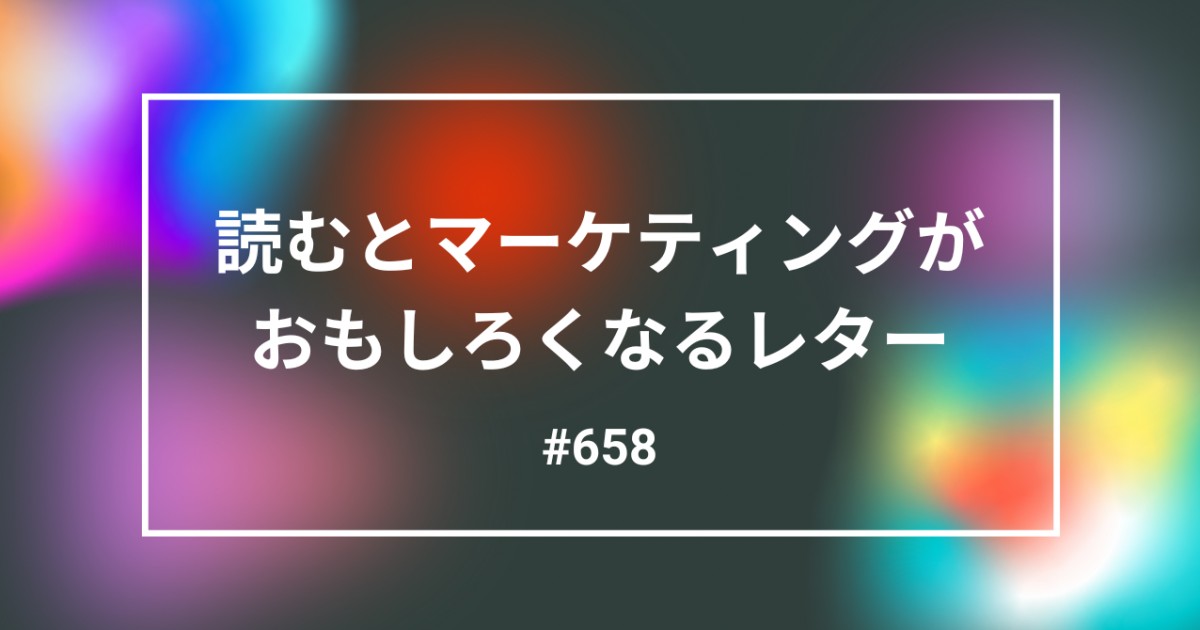#35 マーケティング解説。「◯◯ しかない弁当」 の人気の秘密とは?
こんにちは。メールを開いていただきありがとうございます。
前置きはなくして、本題に入りますね。
レターからわかる内容は、
-
潔すぎる200円ウィンナーだけ弁当 [1つ目のお弁当]
-
10年の年月を経て発売された経緯
-
マーケティング視点で思ったこと
-
100人のうち5人に本当に喜ばれる駅弁 [2つ目のお弁当]
-
幕の内弁当ではダメな理由
-
2つのお弁当から学べること
付録は、
-
戦略を学べるビジネス小説 (おすすめ本)
-
ベネフィットセグメンテーションを解説した動画 (YouTube 紹介)
ローソンストア 100 のウィンナー弁当
最初にご紹介したいのは、ローソンストア 100 のお弁当です。発売は2021年6月30日でした。
以下はローソンストア 100 の公式ツイッターアカウントからのツイートです。

100円ローソンに“おかずがウインナーのみ”の潔すぎる弁当登場 部長が10年間商品部を説得して実現 nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/21… @itm_nlabより #ローソンストア100 #ウィンナー弁当 100円ローソンに“おかずがウインナーのみ”の潔すぎる弁当登場 部長が10年間商品部を説得して実現 部長の熱意がすごい。 nlab.itmedia.co.jp
お弁当の中身はウィンナー5本がメインで、他にはご飯とウィンナーの下にスパゲティが敷かれているだけのシンプル過ぎるお弁当です。お値段は200円 (税込み216円) 。
Twitter で拡散され、ネット系のニュースも後追いで記事にし話題になりました。
ウィンナー弁当の開発経緯
先ほどのローソンストア 100 の公式 Twitter アカウントからのツイートにあったように、ウィンナー弁当は10年の時を経て発売されたとのことです。
正確に言うと研究や商品開発に10年を費やしたのではなく、10年間にわたって社内で要望を出し続けて10年後にようやく商品化が決定しました。
アイデアはある運営部長からでした。「おかずがウィンナーだけの弁当を作って欲しい」 「絶対に売れる」 と10年間、商品部にリクエストを出し続けました。
運営部長の 「絶対売れる」 の根拠は、ローソンストア 100 でよく売れているのがカップ麺、スープ、冷やし麺で、それらと合わせて 「おかずがウィンナーだけの弁当」 が買われるはずだと。おかず一品だけの直球勝負の弁当は 「消費者に絶対に受ける」 という見立てです。
思ったこと

ここからは、ローソンストア 100 のウィンナー弁当の開発と発売から思ったことです。
ウィンナー弁当で思ったこと
-
絞るからお客に刺さる
-
売れ筋からの機会発見 (競争ではなく共存)
では順番にご説明しますね。
[考察 1] 絞るからお客に刺さる
ウィンナー弁当はおかずがウィンナーだけ、シンプルで潔すぎる弁当です。

引用: ねとらぼ
通常、お弁当は複数のおかずが入っていますよね。しかしウィンナー弁当は1つに絞り、しかもウィンナーという言ってしまえばありきたりのおかずです。ここにある発想は、「あれもこれも」 と思いつくものを全て入れるのではなく、引き算の考え方です。
明確に絞っているからこそ、それを欲しいと思う人には 「これは自分向けの商品だ」 と思えます。
ウィンナーだけの直球勝負というコンセプトが明確なので、実際のおかずの中身、ウィンナーの選び方や見せ方、お弁当の名前まで一貫性があります。だからこそ、特定のお客にはグサッと刺さるわけです。
[考察 2] 売れ筋からの機会発見

10年も前からアイデアを思いつき要望を出し続けた運営部長は、実際のローソンストア 100 の店舗での売り筋から考えました。
自分が欲しいというよりも、「お客はきっとこういう商品を望んでいるはず」 という捉え方です。
お店でよく売れるカップ麺、スープ、冷やし麺は一見するとバラバラですが、共通点は1つ1つは単品であることです。単品だけでは消費者はおそらく物足りなく、「満足感を得られないのでは」 という仮説が運営部長の頭の中にはあったのでしょう。
私が興味深いと思ったのは、売れ筋についての解釈です。店頭での売れ筋を見て、例えば 「カップ麺が売れているから新しいラーメンを開発しよう」 ではなく、カップ麺やスープと一緒に食べられるものは何かという発想です。
既存の売れ筋と正面から立ち向かう競争ではなく、アイデア発想のベースには 「他の売れ筋と共存できないか」 という協調路線があります。共存の思想からアイデアを考え、機会 (ビジネスチャンス) を発見したのです。
ここまでローソンストア 100 のウィンナー弁当を見てきました。
思い出したのがある本に書かれていた、これまたおかずは1品だけに絞った駅弁です。
100人のうち5人に本当に喜ばれる駅弁とは?
この本で印象的だったのは、「100人にウケる1つの駅弁よりも、5人にウケる駅弁を20種類あったほうがよい」 という考え方です。以下は本書からの引用です。
シンプルなお弁当のほうがお客様にピッタリ合う場合が多いのです。
たとえば、お肉が食べたい気分のお客様はお肉をお腹いっぱい食べられるお弁当があったらうれしいですし、魚が好きなお客様は魚介類の素材にこだわったお弁当を食べてみたいと思うでしょう。
そしてもう1つ、シンプルなお弁当は、アピールポイントがはっきりしているので、販売スタッフがお勧めしやすいのです。
(中略)
中途半端なおかずがいろいろ入っていて何をアピールしていいかわからないお弁当より、シンプルでわかりやすいお弁当のほうが絶対お勧めしやすいのです。
ただし、そういうシンプルなお弁当はたくさんの人に受けるわけではありません。たとえば、さばだけがドーンと入ったお弁当を100人にお勧めしたとしても、そのお弁当に満足するのは5人くらいです。
でも、5人が確実に満足するお弁当を20種類取りそろえれば、100人全員満足してくれるはずです。
(中略)
もちろん、100人全員が満足してくれる駅弁を開発できるなら、コストを下げて利益を上げるためにもそれが最良の方策です。
でも、100人が確実に満足する駅弁を開発することは不可能です。100人の中には肉が嫌いな人も、魚が嫌いな人もいますから、どんなにおかずを取りそろえて豪華な幕の内弁当をつくっても、このおかずが全部好きという人はごくわずかです。
幕の内弁当ではダメ
昔から定番な駅弁に、幕の内弁当があります。おかずの種類が多く、100人全員が当たり障りなく食べられる駅弁です。しかし、幕の内弁当では 「可もなく不可もなし」 です。
著者の考えは、「幕の内弁当ではなく100人のうち5人だけでいいので、その5人が本当に満足してくれる駅弁が良い」 というものです。
では、100人のうち5人が本当に満足する駅弁とは、どのような駅弁なのでしょうか?
ウニだけに絞った駅弁
本書に紹介されていたのが、ウニだけに絞った駅弁です。
ご飯の上にウニがふんだんに載せられた弁当で、名前は 「平泉 私の好きな金色うにめし」 です。

引用: 斎藤松月堂
ちなみにこの 「平泉 私の好きな金色うにめし」 という駅弁の名前は著者が考えたものです。
うにめしでは弱いので、平泉の金色 (こんじき) 堂から金色を取ったそうです。著者がコンセプトから提案し、自分のイメージ通りに開発した駅弁です。名前に入っている 「私の好きな」 は、文字通り著者自身がこの駅弁が大好きだからとのことです。
絞るからこそ明確になる
このウニ弁当のように素材を1つだけに絞れば、その駅弁のネーミングもユニークなものにできます。単に奇をてらった名前ではなく、その素材を効果的にアピールする駅弁名称をつけることができます。
素材を絞る効果は、実際に販売する駅弁販売員にも良い影響を与えます。お客さんにアピールできる点が明確なので、販売員が説明をしやすいわけです。お客さんにとっても、自分がその1つの素材が使われたお弁当を食べたいか食べたくないかが判断しやすいです。
今回のレターで最初にご紹介したローソンストア 100 のウィンナー弁当も、本質的には同じです。
ポイントは、100人中5人でよいという振り切りです。もし、100人のうち30人や20人などであれば、絞り方は中途半端です。
最後に
そろそろ今回のレターも終わりです。ここまで読んでいただきありがとうございます。
今回は2つのユニークな弁当を取り上げました。コンビニ弁当と駅弁に共通するヒットの秘密を掘り下げ、商品開発やマーケティングに学べることを見てきました。
ポイントを1つ挙げるなら 「絞るからこそ価値が伝わる」 です。戦略の肝は 「やらないこと」 にあり、絞っていくと 「やること」 が明確になります。誰に対して、何を、どこで、いつ、どうやるかも絞るからこそ見えてきます。
これは個人のレベルでも同じです。やることが多すぎると感じる時は、「どれからまずやるべきか」 を考える前に 「何をやらないか」 に立ち返ってみてください!絞るからこそやることが明確になるはずです。
今週のおすすめ本
今回のレターは、一言で言えば 「戦略的な絞り」 でした。
関連しておすすめのビジネス小説があります。本のタイトルは、戦略プロフェッショナル - 競争逆転のドラマ (三枝匡) です。
ストーリーの肝のところなので詳しくは触れませんが、この本の見どころはターゲット顧客の設定です。
事業戦略をつくるにあたってのセグメント (参入市場の分解) と、ターゲティング (分けたセグメントのうちどこを狙うか) を小説のストーリーで興味深く読めます。ポイントは 「顧客の絞り」 で、今回の2つのお弁当にも通じます。
小説としてもおもしろく、何より戦略の教科書としても勉強になる1冊です。よかったらぜひ読んでみてください。
今週の YouTube
先ほどのおすすめの本でセグメンテーションとターゲティングに触れました。
今回の YouTube は、セグメンテーションについての動画のご紹介です。ベネフィットセグメンテーションのつくり方、メリットとデメリットを解説しています。
ちなみにメリットはセグメンテーションから打ち手につなげやすいこと、デメリットは作ること自体が難しいことです。
[マーケティング STP] ベネフィットセグメンテーションを解説
レター作成者
多田 翼
Aqxis 合同会社 代表 (会社概要はこちら)
主な事業
マーケティング, マーケティングリサーチ, 事業戦略などのコンサルティング事業
※ お問い合わせは会社 HP からご連絡ください
経歴
Google でシニアマーケティングリサーチマネージャーを経て独立。Aqxis 合同会社を設立し代表に就任。Google 以前はインテージにてマーケティングリサーチ業務に従事。
京都大学大学院 工学研究科 修了。
・マーケティングのことが学べる
・人気商品のヒット理由がわかる
・仕事でマーケティングや商品アイデアのヒントになる
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績