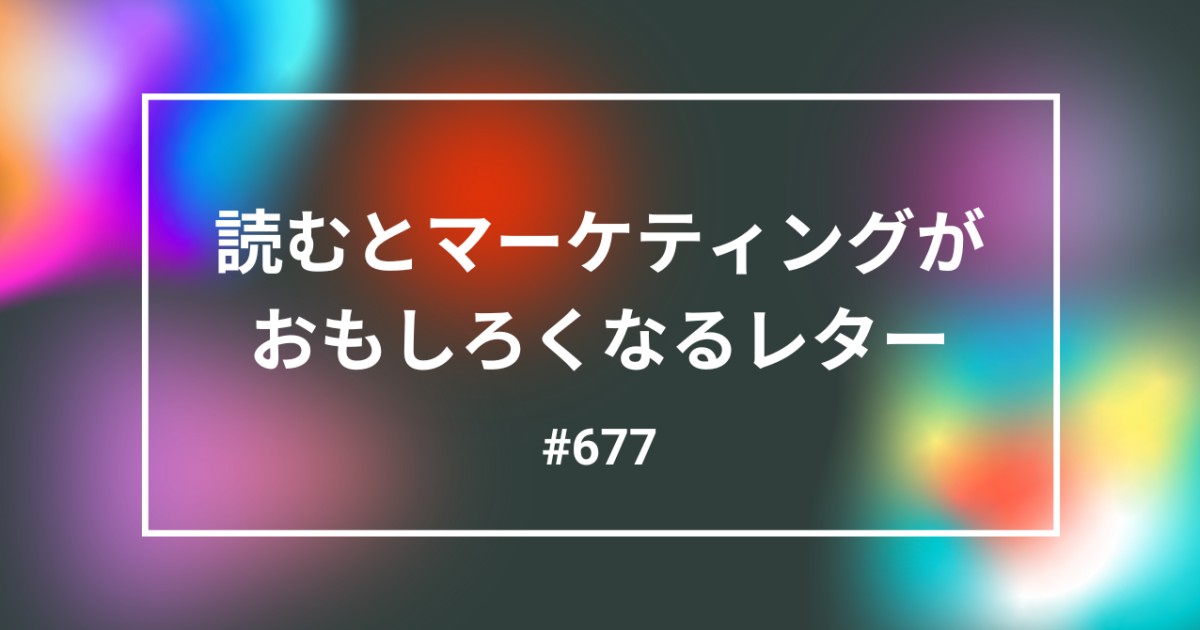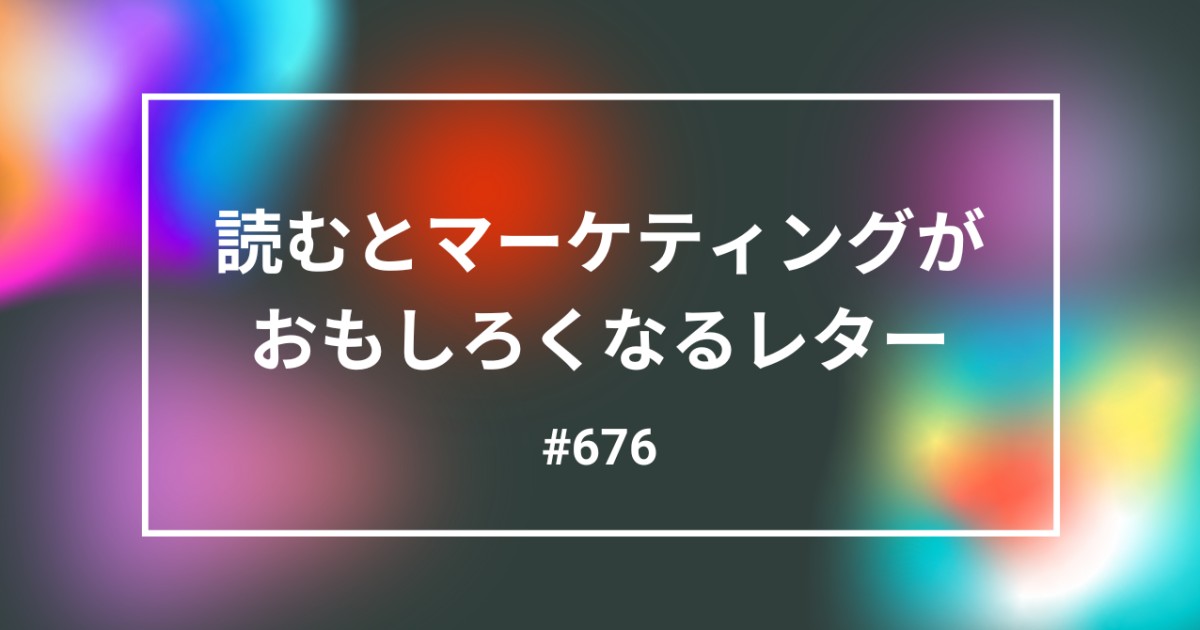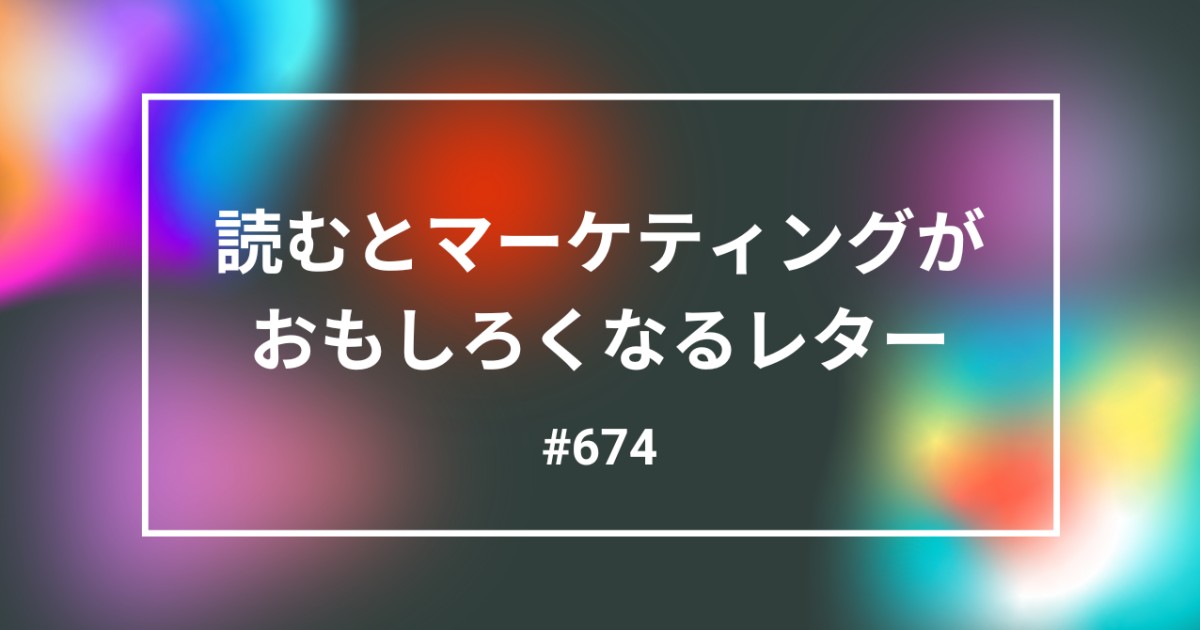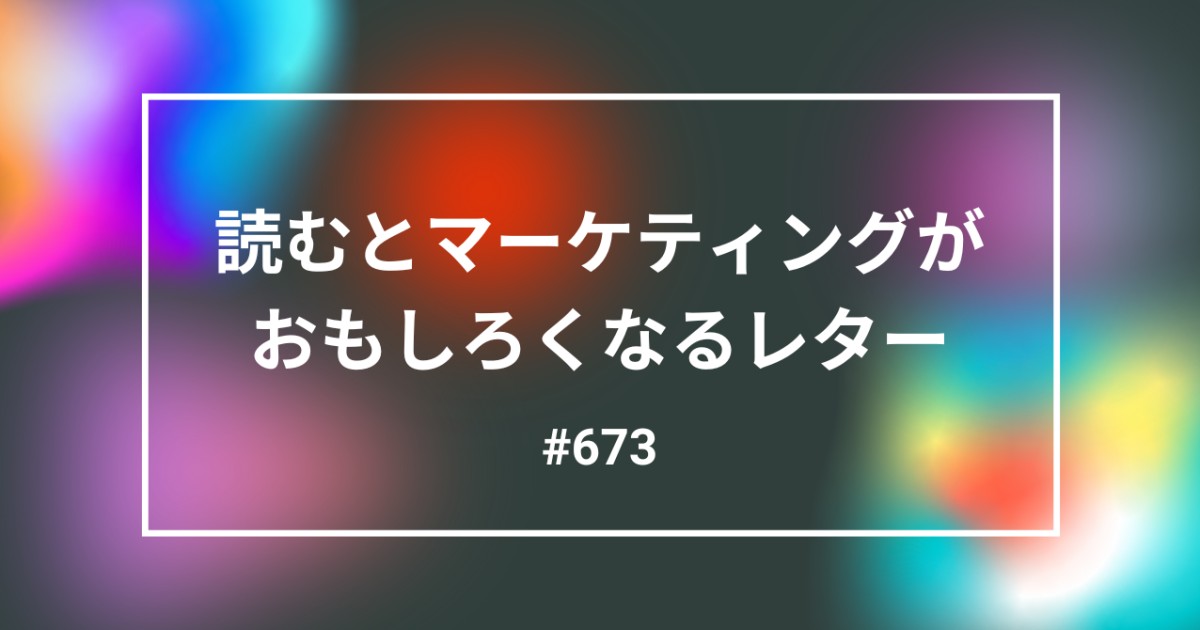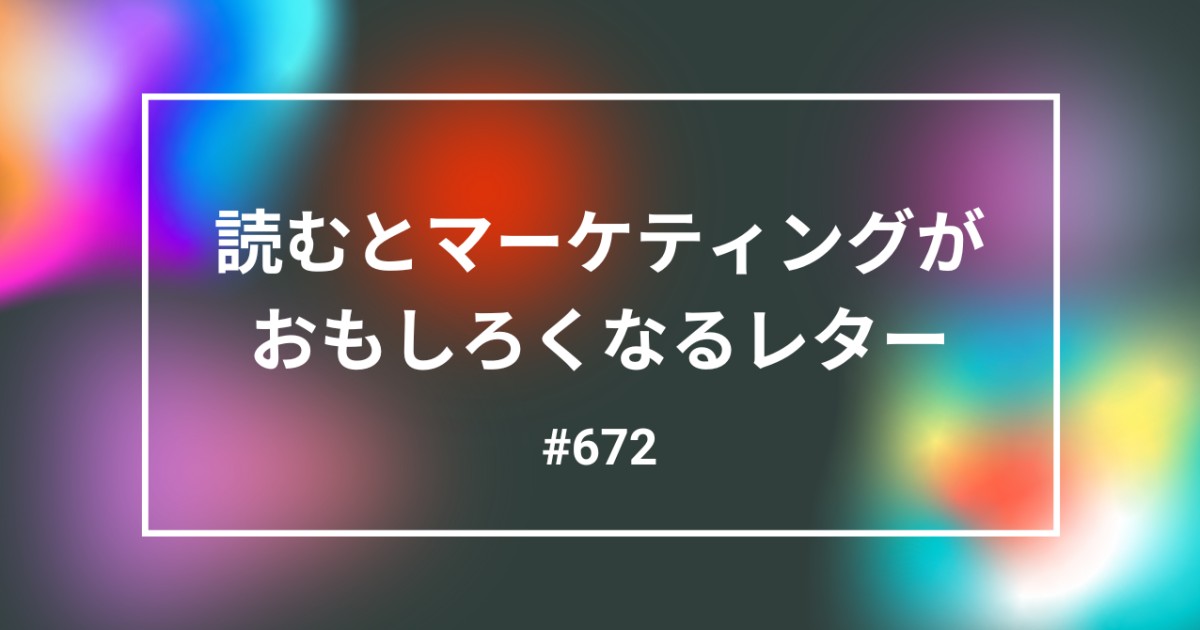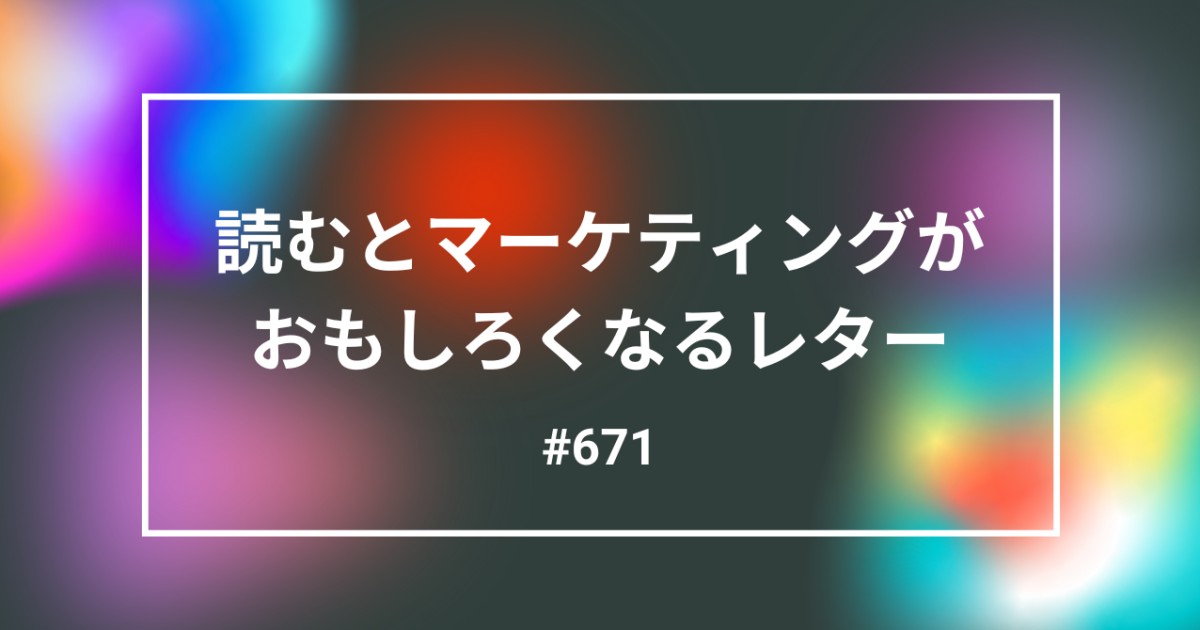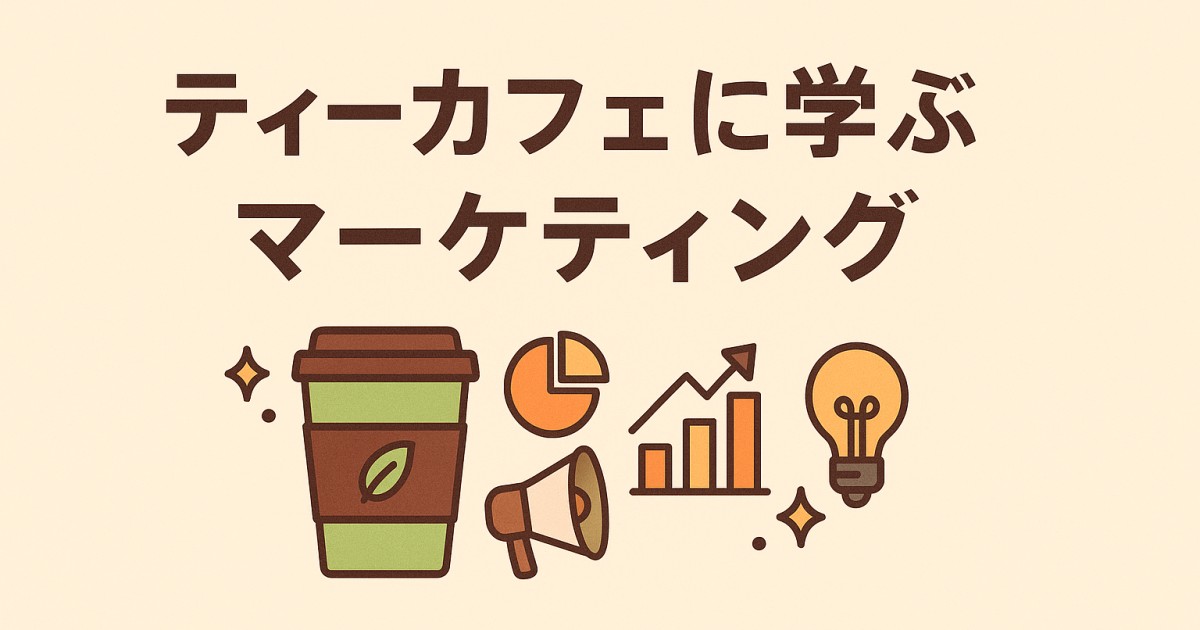#2 戦略の Why を明確にし自分ごと化しよう
今回のキーワードは 「戦略」 と 「Why」 です。
Why は戦略の上位にあるものです。Why を明確にし自分ごと化する大切さと、その具体的な方法を事例を交えながらご紹介していきます。
ぜひ記事を最後まで読んでいただき、お仕事での参考にしてみてください。
戦略とは

最初にそもそも戦略とは何かです。もし 「戦略とは何か」 とあらためて聞かれれば、読者の皆さんはどのようにお答えになるでしょうか?
戦略については私の一言の定義があるので、このレターではそれをご紹介させてください。
戦略とは目的を達成するための 「やること」 と 「やらないこと」 の決めごとです。
第一回のレターで書いたように、戦略の肝は 「何をやらないか」 にあります。多くの選択肢のある中でやらないことを決め、残った 「やること」 に自分たちのリソースを集中的に配分します。
戦略と目的
戦略で大事なことは上位にある目的への意識です。
先ほどの定義のように、戦略は目的を達成するためにあります。この意味で戦略は手段です。
ところで 5W1H がありますよね。
5W1H で言えば、目的は Why です。Why に対して戦略は What です。そして戦略の具体的な実行プランである戦術は How です。
このような Why, What, How で整理をすると戦略の位置づけが明確になるので、5W1H の中でもこの3つはよく使うので覚えておいて損はないです。
Why に立ち戻る

ではここからが今回のレターで皆さんにお伝えしたいことです。Why をどのように設定すればいいかです。
よく起こりがちなことに 「手段の目的化」 があります。ここまでの文脈に当てはめれば、What や How がいつの間にか Why に置き換わってしまう状況です。本来の Why が忘れ去られてしまうのです。
それでは身近なビジネスの例で、どんな状況が手段の目的化になってしまうのかを見ていきましょう。
手段の目的化の例
例えば会議です。皆さんは普段のお仕事で、どんな会議に参加されているでしょうか?
ここでは 「毎週の定例会」 を例に、手段の目的化を考えてみましょう。
定例会の目的は何でしょうか?目的はメンバーが集まり、お互いの進捗確認と問題解決のための意見出しとします。これが Why です。
What は個別のメンバー間のやりとりではなく、定例としての会議を持つことです。
How は具体的な定例会の運用内容です。具体的には決まったフォーマットで各メンバーから進捗報告をしてもらい、前週ハイライトとローライト、今週のアクションを発表します。参加者には事前に提出してもらい、読み込んだ上で会議に出席してもらうといいでしょう。
しかし、ここで手段の目的化が起こります。
会議がある前提になると非効率な面が出てきます。例えば、Slack などのチャットでメンバーに見えるところでさっと共有すれば済むことでも、会議に持ち込まれるようになります。
会議という手段が、いつの間にか会議をすること自体が目的にすり替わってしまうのです。もともとの目的は円滑な情報共有と問題解決でしたが、手段の目的化によって元の目的が達成されなくなります。
このように Why が忘れられ、What であった会議実施が前提になってしまっていないでしょうか?
Why の設定方法の例
それでは具体的に Why の設定方法をご紹介します。
私が以前に働いていた Google での話です。今は独立をしていますが、会社員を辞めるまでは5年5ヶ月 Google に在籍していました。
常に問われた 「Why Google」

Google にいた当時に意識していたのは 「Why Google」 を明確にすることです。上司や周りの同僚から問われたり、自分自身にも問いかけていました。
では 「Why Google」 とは何でしょうか?
Why Google とは案件やプロジェクトをやるにあたって、「なぜ Google がやるべきなのか、他ではなく Google がやる意義は何か」 です。
私自身の当時の仕事で Why Google とつなげていたのは、Google のミッションです。
ミッションの自分ごと化
Google のミッションをお聞きになったことはあるでしょうか?
Google の使命は、「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること」 です。もとの英語は "Organize the world's information and make it universally accessible and useful." です。
使命として掲げるこの壮大なミッションを、Why Google として自分の仕事に落とし込むようにしていました。
具体的には、次のような自分やプロジェクトへの問いかけです。
-
この仕事はどんな情報を整理することなのか
-
具体的にどのように整理をしていくのか
-
一人でも多くの人に役に立つものか
私の Google での最終的なポジションは 「シニアマーケティングリサーチマネージャー」 でした。
マーケティングリサーチに Google のミッションを当てはめれば、リサーチ結果というファクトだけでは終わらせずに、マーケティングの意思決定やアクションにつなげる示唆までを提示するようにこだわっていました。
では、もう少し具体的に当時の私がどのようにこだわっていたのかをご紹介させてください。
マーケティングリサーチでの例
マーケティングリサーチの結果報告で単にグラフをつくって綺麗に見せるだけではなく、マーケティング戦略や施策へリサーチャーの立場からの提案です。
例えば Google 検索のユーザーを調査した時の話です。
分析結果をただファクトとして示すだけでは足りません。ユーザーインサイトを深く掘り下げ、インサイトに沿ってのマーケティングコミュニケーションのアイデアを出しました。
例えば、Google 検索サービスのプロダクトマーケティングマネージャーに、こちらからの示唆を積極的にぶつけ議論をしました。そうすることにより、相手にはなかった視点でのマーケティング施策への気づきになります。
マーケティングリサーチから示唆を出し、意思決定やアクションに少しでも貢献する姿勢は、Google のミッションを自分ごと化するために大切にしていたこと、そして何よりリサーチャーとしての譲れない矜持のようなものです。
価値基準からの Why Google

もう一つ Why Google のエピソードをご紹介しますね。
Google が文化のように大切にする価値基準から Why Google への答えを見出していました。
具体的には例えば 「ユーザーファースト」 や 「正しいことをやる」 です。
後者の正しいことをやるへの補足です。もともとは 「Don't be evil (邪悪になるな) 」 で、正しいことをやるという Google が大切にする 「Do the right things」 を意識していました。
ここで言う正しいこととは Google にとってだけではなくユーザーにとってと、さらにその先の世の中全体にとって正しいかどうかという判断基準です。
「世界をより良くする」
Google では 「社会を良くする」 と本気で考え仕事をする人が普通にいました。
例えば Google の同僚と会議をしていると、自然と会話の中で 「Make the world better place」 という表現が出てきたのを今でもよく覚えています。意味は 「世界をより良くする」 です。自分たちが暮らしている世界を少しでも良くしたいという思いが入った言葉です。
先ほどの 「Do the right things」 もそうで、絵空事でなはく判断基準として意思決定に使われていました。そんなカルチャーや雰囲気の中で仕事をできたことは自分にとって良い経験になりました。
Why を自分ごと化しよう
ここまでの話を整理しますね。
仕事での戦略とは、自分がやることとやらないことの大きな方針を決めることです。
やること・やらないことの上位には仕事の存在意義や目的があります。これらが Why です。

存在意義や目的である Why と戦略 (What) をセットにして積み重ねていくことによって、仕事から自分のキャリアができていきます。
その方法が例えば今回ご紹介した、ミッションや価値基準などの経営理念からつなげて自分ごと化する方法です。
今日のアクション
そろそろ今回のレターも終わりです。ここまで読んでいただきありがとうございます。
今回は戦略の上位にある 「Why」 をキーワードに、皆さんと一緒に Why の自分ごと化を見てきました。いかがだったでしょうか?
今回のレターから、何かアクションにつながりそうなヒントをお伝えすることはできたでしょうか?
ぜひ今日のあなたの仕事から、目の前のことの 「そもそもの Why は何か」 をほんの少しでもいいので立ち止まって意識してみてください。
もしかしたら当初の目的や位置づけから、気づかないうちにやっていることがズレてしまっているかもしれません。そんな時は Why に立ち返ってみませんか?
さらにもう一つ、会社のミッション、皆で大切にしたい文化や価値観を体現しようとしているかも見直してみてはどうでしょう?
視座が高まったと感じたり、今までになかった自分の内側からのモチベーションにつながるはずです。
最後にあらためての質問です。あなたの Why は何ですか?
レター作成者
多田 翼
Aqxis 合同会社 代表 (会社概要はこちら)
経歴
Google でシニアマーケティングリサーチマネージャーを経て独立。Aqxis 合同会社を設立し代表に就任。Google 以前はインテージにてマーケティングリサーチ業務に従事。
京都大学大学院 工学研究科 修了。
主な事業
マーケティング, マーケティングリサーチ, 事業戦略などのコンサルティング事業
※ お問い合わせは会社 HP からご連絡ください
・マーケティングのことが学べる
・人気商品のヒット理由がわかる
・仕事でマーケティングや商品アイデアのヒントになる
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績