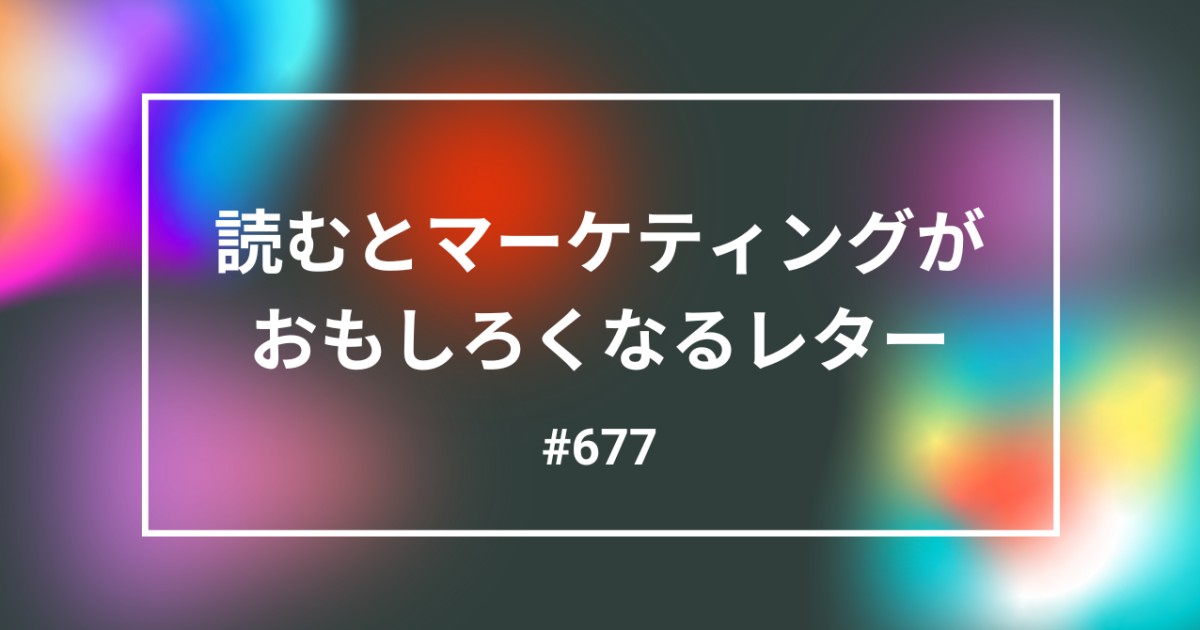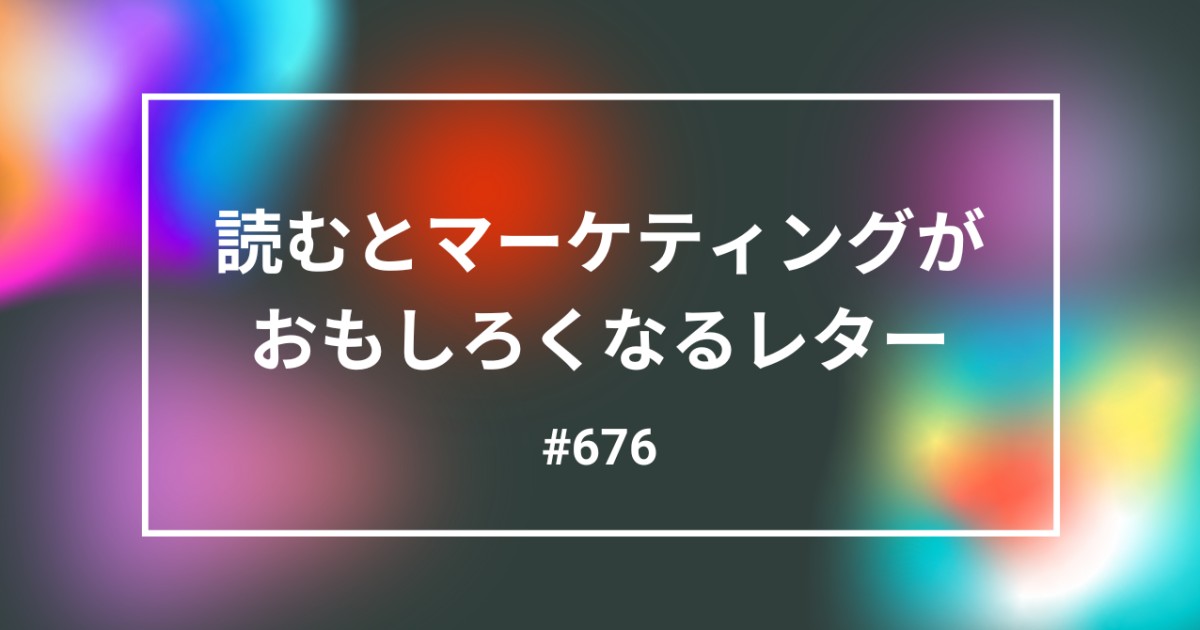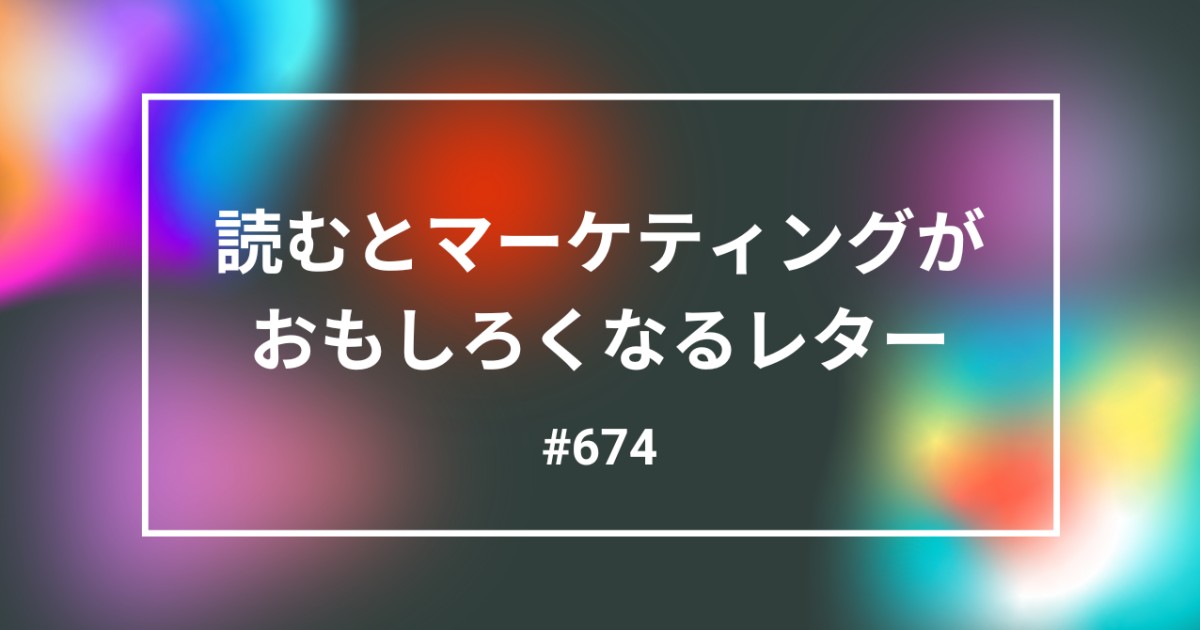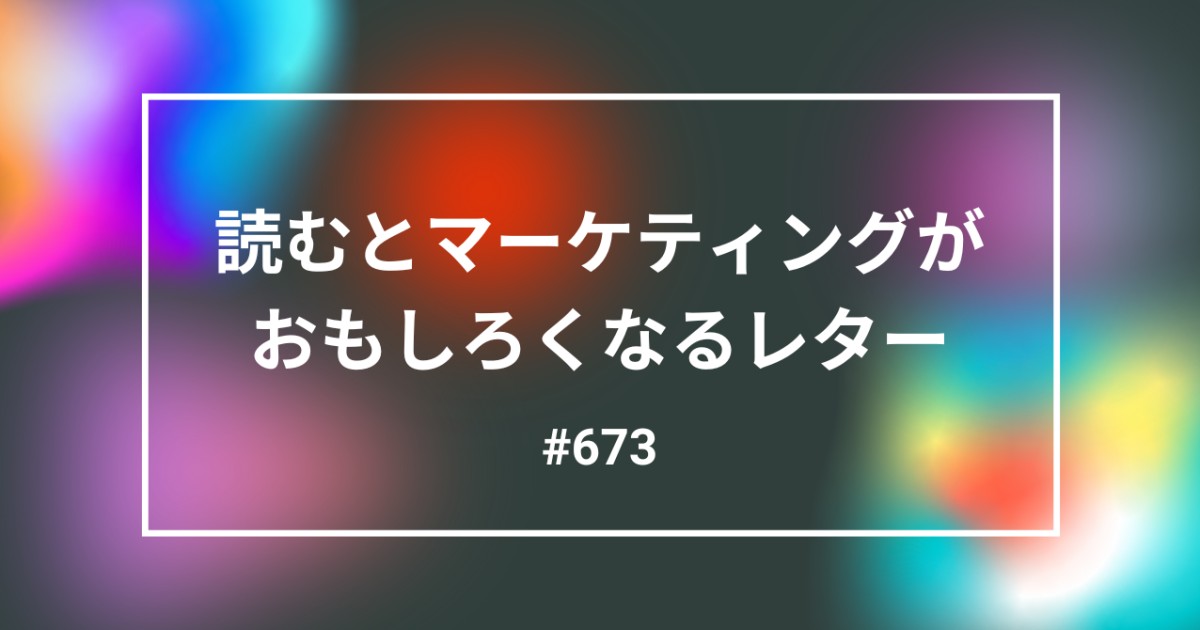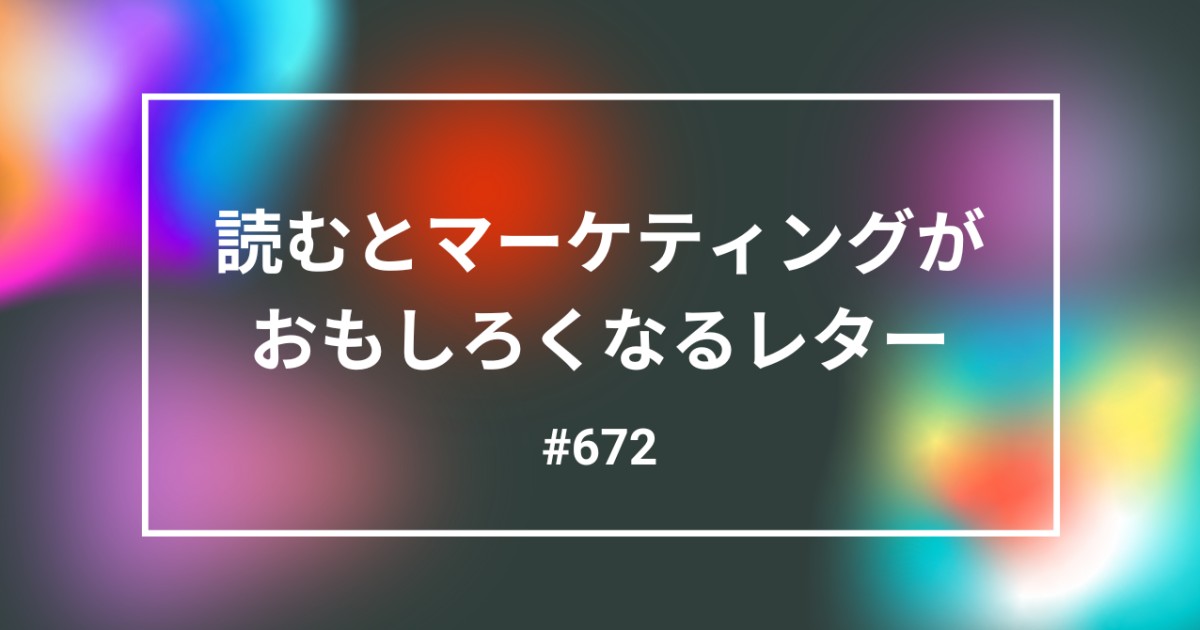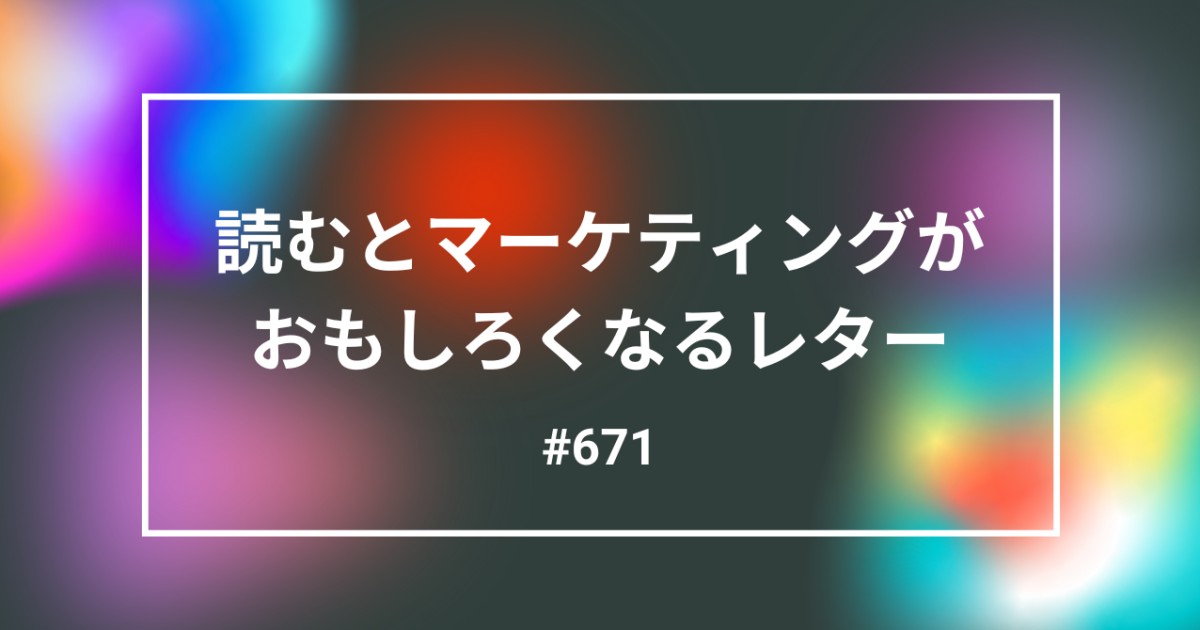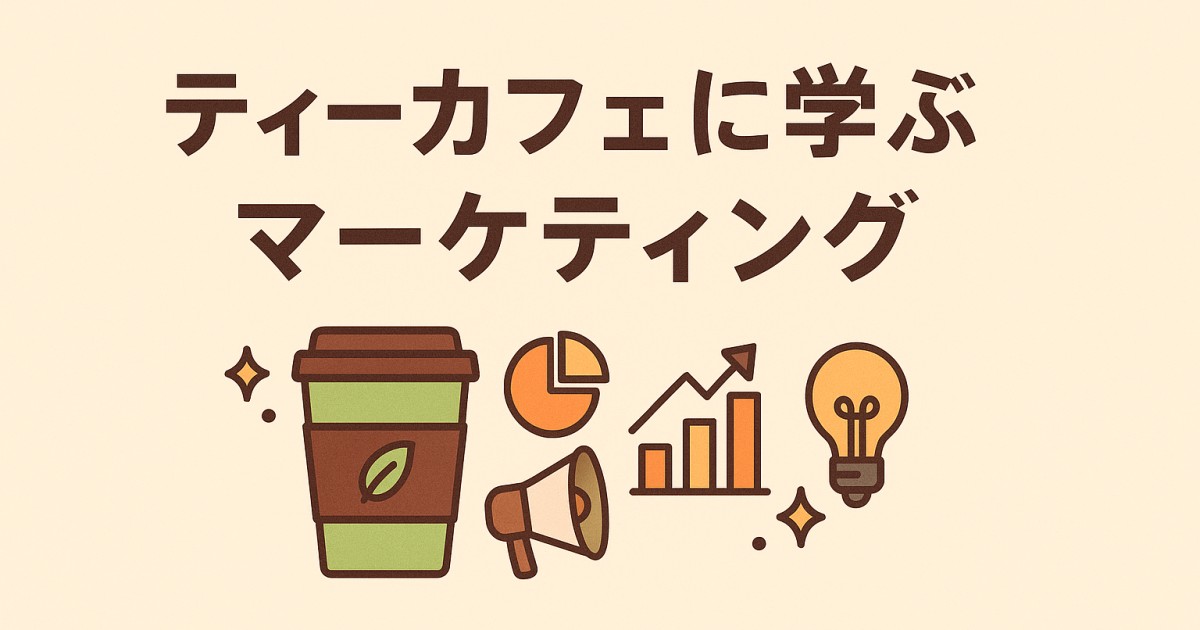#33 Google で活躍する人は ◯◯◯◯ 。貪欲に学ぶ方法をご紹介
こんにちは。メールを開いていただきありがとうございます。
今回のテーマは 「学習」 です。
レターからわかる内容は、
-
Google で活躍する 「ラーニングアニマル」 とは
-
学びは 「人」 「本」 「体験」 から
-
読書からの学習方法 (6つ)
-
超効率勉強法 (今週のおすすめ本)
-
Google の同僚で尊敬する人の話 (今週の YouTube)
では早速、Google で活躍する人の特徴である 「ラーニングアニマル」 から見ていきましょう。
Google で活躍する 「ラーニングアニマル」
How Google Works - 私たちの働き方とマネジメント という本は、興味深く読むことができた本でした。
印象的だったのは 「ラーニング・アニマルであれ」 でした。
以下は本からの引用です。
とびきり優秀な人でも、変化のジェットコースターを目の当たりにすると、もっと安全なメリーゴーランドを選ぼうとするケースはやまほどある。心臓が飛び出しそうな体験、つまり過酷な現実に直面するのを避けようとするのだ。
ヘンリー・フォードは 「人は学習を辞めたとき老いる。20歳の老人もいれば、80歳の若者もいる。学びつづける者は若さを失わない。人生で何よりすばらしいのは、自分の心の若さを保つことだ」 と言った。
グーグルが採用したいのは、ジェットコースターを選ぶタイプ、つまり学習を続ける人々だ。彼ら ”ラーニング・アニマル” は大きな変化に立ち向かい、それを楽しむ力を持っている。
ラーニングアニマルの特徴
ラーニングアニマルな人は、学ぶことに貪欲です。
自分のまわりを見て、あらためてラーニングアニマルだと感じる人がいます。常に新しいことを学び続けています。単に学ぶだけというわけではありません。学習を続けるだけではなく、学んだことを 「次」 に活かしているのです。
「学ぶ → 学習内容を活かして成果を出す → 学ぶ → … 」 、という好循環のサイクルを回し続けているように見えます。それも小さく早く回しています。
もう1つ特徴を上げると、ラーニングアニマルの人たちは何を学ぶべきかの取捨選択の基準が明確です。本人の中でいくつもの課題意識があり、そのアンテナに引っかかったものを深掘りしていきます。
一方で、途中で何か違うと感じたり、これ以上は必要なさそうだと思えば、その時点で止めます。結果、広げすぎず、その時々で必要なことに絞って学びを続けています。
ここまでラーニングアニマルについて見てきました。
ところで学びの対象を大きく俯瞰すると、人から、本から、体験からの3つです。ではここから先は、2つ目の 「読書からどう学ぶか」 を掘り下げてみます。
読書からの学習方法

ご紹介したいのは、「学びにつなげる読書方法」 です。次の6つです。
読書からの学習方法
-
目的と余白
-
ウォーリーを探せ
-
想起と再言語化
-
その場シミュレーション
-
アウトプット
-
守破離からの実践
中には 「何のこと?」 というのもあったかもしれませんが、順番に解説していきますね。流れは読書前、読書中、読書後です。
[1: 読書前] 目的と余白
可能な限りで、これから読もうとしている本の目的を明確にします。目的は何かを自分の言葉で言語化するといいです。
目的の明確化
-
どんな必要性で読むのか (読書の背景)
-
その本に期待すること (知りたいこと, 得たいこと)
-
どんなことに活かせそうか
なお、必ずしも全ての本に目的を明確にする必要はないです。というのは、目的をきっちりと固めすぎることの弊害もあるからです。
目的から逆算した読書では、本の内容から偶然での思わぬ発見に気づけなくなります。効率を重視するあまりにインプットへの余裕がない状態です。
目的を持つとともに、ガチガチに目的に縛られない余白も大事です。
[2: 読書中] ウォーリーを探せ
いきなりですが、ウォーリーを探せの本を読んだことはあるでしょうか?
絵の中にはたくさんの人や動物、物が描かれていて、どこかに潜むウォーリーを見つけるのに、なかなか発見できないこともあります。
絵本を読むのに、「ウォーリーはどこか」 という意識がなくただ眺めているだけでは、ウォーリーは見つからないでしょう。
読書を仕事に活かすのも、これと同じです。自分はこれからどんなテーマで本から学ぶのか、具体的に今やこれからの仕事にどう活かしたいかです。自分にとってのウォーリー、つまり本から何を獲得するかが明確なほど、仕事などに活かす情報が得られます。
あなたにとってのウォーリーは、本で著者が書いたテーマと同じこともあれば、本の主題とは異なることもあります。前者は例えばマーケティングの本からマーケティングを学ぶ、後者は小説や時にはマンガ・絵本からビジネスのことに学びを得る読書です。
[3: 読書中] 想起と再言語化

3つ目の方法は 「想起と再言語化」 です。読みながら適宜のタイミングで、自分の理解を言葉にします。
タイミングは例えば1つの章を読み終えたら本を閉じ、書かれていた内容を3つのポイントでまとめたり、自分が思ったことを3つに絞って言語化してみます。
不明点や疑問点を言葉にするのもいいです。
ここでのポイントは、本文に書いてあった表現をそのまま暗記しようとするのではなく、自分で言葉に直して言ってみると良いです。場所や状況にもよりますが、独り言のように口に出してみると効果的です。
もう1つは読みながら新しく得た知識や方法を、仕事などどこかで使えないかを考えます。
これが次の4つ目の方法です。
[4: 読書中] その場シミュレーション
読みながら仕事で使えると思ったら、その場で頭の中でシミュレーションをしてみます。実際に使う場面を具体的にイメージしてみるのです。
これは 「その場ですぐに」 がポイントです。2~3分でもいいので、本を読むのを止めて考えてみます。例えば、このフレームは今考えている企画に使えると思えば、実際にそのフレームに仕事の内容を当てはめてみます。
会社へ向かっている通勤中なら、その後に会社に行った後にもう一度使ってみます。一度頭の中でやっているので、読書で得たことが反復でき、定着しやすくなります。
[5: 読書後] アウトプット

読み終わった後に総まとめとして、思ったことをアウトプットします。
私が具体的にやっているのは、紙のノートの 1-2 枚で頭の中のことを書いてはき出します。
ここでもやっていることは 「想起と言語化」 です。記憶は何度も思い出すことにより定着します。読んだ後に必ず紙ノートに落とし込むという意図的に想起する機会をつくります。
ここでも1つでもいいので、本の内容を実際に実践できないかを意識すると良いです。書かれてあった内容をそのまま真似してもいいですし、自分なりにアレンジしてみてもいいので、実践の仕方は自由な感じでです。
[6: 読書後] 守破離からの実践
6つ目の方法は守破離です。
守破離とは簡単に補足をすると、
守破離
-
守: 師匠や先生を徹底的に真似する
-
破: 少しずつ自分のやり方を入れアレンジしていく
-
離: 完全に自分のやり方を確立する
読書を仕事に活かす方法でも、守破離のアプローチは読書にも有効です。具体的には次のようなやり方で、本での学びを自分のものにしていきます。
読書の守破離
-
[守] 本で書かれていたことを、同じように真似をしてやってみる
-
[破] 必ずしも自分の仕事・業務にはフィットするとは限らず、少し変えて適応させる (工夫を入れる)
-
[離] 自分の型にし、本で学んだことが自分のものになる
大事なことは、まずは真似でいいので試してみることです。この時のポイントは、うまくいかないかもしれないという失敗を想定しておきます。
著者と自分では状況が違うなど、前提が同じとは限りません。前提が異なれば、同じことをやってもうまくいくこともあれば、うまく機能しないこともあります。そのまま真似をしてうまくいかなかった後に、自分なりの工夫を入れて活かすといいです。
最後に
そろそろ今回のレターも終わりです。ここまで読んでいただきありがとうございます。
今回は 「学習」 をテーマに、Google で活躍する 「ラーニングアニマル」 、後半は読書にフォーカスを当てて学びを深める読書方法を見てきました。
これは自分自身への課題感でもありますが、少しでもラーニングアニマルのような何ごとにも貪欲に学ぶ姿勢を忘れないようにしたいと思っています。学びの対象は 「人」 「本」 「体験」 で今回は読書についてでしたが、人や体験から日々学びを続けたいです。
読書方法をご紹介したのは自分のやり方を整理する意味もありました。本の読み方は10人いれば10通りがあり、皆さんご自身の読み方があると思います。何か少しでも参考になればうれしいです。
今週のおすすめ本
勉強法で参考になった本をご紹介します。
この本の内容を一言で言えば、アクティブラーニングの具体的な効果と方法が紹介されている本です。
アクティブラーニングとは、積極的に頭を使って学習していく方法で、やらされの受け身ではなく能動的な学習スタイルです。インプットとアウトプットを同時にやる学習とも言えます。
勉強中だけではなく、勉強の前後にもアクティブラーニングを取り入れる方法が紹介されています。
-
勉強前の準備からアウトプットをする
-
勉強中に積極的に自分の理解をテストする
-
勉強後も記憶を思い出す機会をつくる
-
運動や音楽を効果的に使う
-
昼寝や休憩をうまく取り入れる
よかったら読んでみてください。
今週の YouTube
レター本文では Google で活躍する 「ラーニングアニマル」 を取り上げました。関連して、Google で働いていた時の同僚のことを紹介した動画です。
Google の同僚で尊敬する人の話。特徴は、① 発想力、② 表現力、③ 論理力
レター作成者
多田 翼
Aqxis 合同会社 代表 (会社概要はこちら)
主な事業
マーケティング, マーケティングリサーチ, 事業戦略などのコンサルティング事業
※ お問い合わせは会社 HP からご連絡ください
経歴
Google でシニアマーケティングリサーチマネージャーを経て独立。Aqxis 合同会社を設立し代表に就任。Google 以前はインテージにてマーケティングリサーチ業務に従事。
京都大学大学院 工学研究科 修了。
・マーケティングのことが学べる
・人気商品のヒット理由がわかる
・仕事でマーケティングや商品アイデアのヒントになる
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績